Q&A
よくある質問
Q&A
2025.09.01
週休3日制を導入する場合、年休の取扱いをどうするべきか?
Q.週休3日制の導入を検討しています。やり方としては1日の所定労働時間(8時間)を増やさず、給与を減らす方向で考えています。この場合、年次有給休暇の付与日数の変更、年休の年5日取得義務の取扱いをどうするべきでしょうか。また、夏季休暇、年末年始休暇を縮減することは可能でしようか。
【通常の労働者と同様に措置】
A.年休は「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(労基法39条1項)とされています。
一方で「1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者」等については、労基法施行規則24条の3第3項に基づき、「通常の労働者」に付与する年休よりも少ない日数が比例付与されます(労基法39条3項)。ただし年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外(労基法施行規則24条の3第3項)としていることから、1週間の所定労働日数が4日(週休3日)の場合であっても、1週間の所定労働時間数が合計30時間以上となる場合については、通常の労働者と同様に、労基法39条1項・2項に定める日数の年休を付与する必要があります。したがって週休3日制度の労働者は30時間以上となるので年休の比例付与の対象とはなりません。
年休の時季指定義務については、労基法39条7項で「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日をいう。以下この項については同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」とされています。そのため基準日に付与される年休の日数が10日以上となる労働者について、その者の1週間の所定労働日数が4日や3日であっても、使用者は基準日から1年以内に、5日の年休の時季指定をする必要があります。
年休以外の夏季休暇や年末年始休暇について、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則において定めを置くこと(労基法89条1項)以上に、労基法では特段の規定を設けていません。しかし、週休3日制を導入する際に、既にある休暇の制度を廃止したり、休暇の日数を縮減したりすることは、労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。特に夏季休暇や年末年始休暇が有給の場合、週休3日制の導入により年間休日日数が増えることを加味しても、増加する休日が無休であることを鑑みれば不利益性は否定できません。特別の休暇制度を安易に縮減するのは避けるべきでしょう。
(以上)
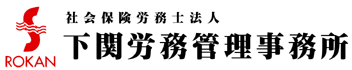









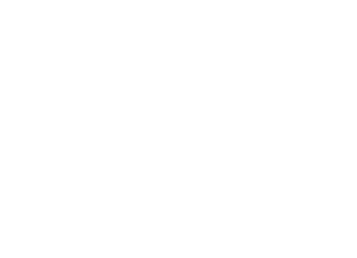
 お問い合わせ
お問い合わせ